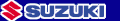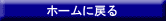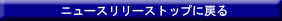2003年2月14日
スズキ財団平成14年度科学技術研究助成について
財団法人 スズキ財団(理事長 鈴木 修)は、2月14日、全国の大学等から応募のあった助成申請に対して、平成14年度の科学技術研究助成として29件、助成総額3,720万円を決定した。 なお、平成13年度の助成は30件、総額3,730万円であり、平成14年度は前年とほぼ同水準の助成を決定した。
今回研究助成を行うものは、生産関連技術6件、環境・省エネルギー関連技術4 件、計測・制御関連技術5 件、材料関連技術5 件、電子・エレクトロニクス関連技術4 件、医療・人間工学関連技術3件、ロボット関連技術2 件の合計29件であり、いずれも独創的、先進的な研究開発テーマである。
具体的には、
| ・ |
生産関連では、アルミ合金溶融炉の電力エネルギー消費量低減に関する研究や、自動車用アルミ合金板のプレス成形技術の改善・発展を目指した研究 |
(※1) |
| ・ |
環境・エネルギー関連では、システムのシンプルさを生かした小型ダイレクトメタノール燃料電池のバイクへの応用に関する研究 |
(※2) |
| ・ |
計測・制御関連では 大気粉塵粒子をターゲットにしたモニター機器開発に関する研究、ナノのレベル等の計測・加工等を視野にした軟X線レーザーに関する研究 |
(※3) |
| ・ |
材料関連では 破壊メカニズムを解明し、セラミックス材料の信頼性向上を目指した研究 |
(※4) |
| ・ |
電気・エレクトロニクス関連では 紫外光照射による光機能性デバイスに関する研究 |
(※5) |
| ・ |
人間工学・医療関連では 移動体の乗り心地に関する研究 |
(※6) |
| ・ |
ロボット関連では 多関節型と直行型ロボットの中間にあたるロボットに関する研究 |
(※7) |
など、今回も広い分野の研究テーマに助成がなされた。
(助成対象研究一覧は別紙の通り)
(※1= 別紙一覧のNo.5、No.9の研究課題、※2= No.18の研究課題、※3= No.22、No.8の研究課題、※4 =No.10の研究課題、※5=No.12の研究課題、※6= No.24の研究課題、※7= No.19の研究課題)
同財団はスズキが創立60周年の記念事業として基金を寄託し、昭和55年3月に設立したもので、本年で23回目の研究助成となる。また、同財団では国際会議の開催や海外の学会等への渡航費の助成、海外からの研究留学者の受入助成、財団ニュースの発行等の活動も行っている。
設立以来の助成内容は、総件数706件、累計助成総額8億7644万円の実績となっている。また財団の資産総額は約29.4億円に達している。
| ● |
スズキ財団の概要 |
| ・ |
財団名 |
財団法人 スズキ財団 |
| ・ |
所在地 |
東京都港区東新橋2-2-8 スズキビル東新橋(TEL 03-5473-7871) |
| ・ |
理事長 |
鈴木 修 (スズキ株式会社 取締役会長) |
| ・ |
目 的 |
国民生活における利便の増進に資する機械等の生産及び利用、消費に関わる科学的研究の助成とその成果の普及を通じて、日本の機械工業の総合的な発展と国民福祉の増進に寄与する事を目的とする。 |
| ・ |
資産総額 |
約29.4億円(平成14年4月1日現在) |
|
| No. |
研究課題 |
機関名 |
役職 |
代表者 |
| 1 |
高機能流体の非線形挙動を利用した高効率の振動制御 |
東京大学 |
助教授 |
阿部雅人 |
| 2 |
担持バリウム触媒による自動車排ガス中の窒素酸化物の直接分解除去 |
京都大学 |
助手 |
岩本伸司 |
| 3 |
船の自動着岸に関する研究 |
千葉大学 |
助手 |
大川一也 |
| 4 |
バイオマテリアルの超精密表面改質加工の研究開発 |
理化学研究所 |
基礎科学
特別研究員 |
片平和俊 |
| 5 |
酸水素炎熔融法によるアルミニウムダイキャスト用インゴットに関する研究 |
静岡大学 |
教授 |
金子正治 |
| 6 |
「有機ハイドライド」を利用するポータブル燃料電池の基礎技術研究開発 |
北海道大学触媒化学
研究センター |
講師 |
仮屋伸子 |
| 7 |
水中水噴流ピーニング材の残留応力測定によるギア疲労強度強化メカニズムの解明 |
埼玉工業大学 |
助教授 |
巨東英 |
| 8 |
新型高性能軟X線レーザーの物理の解明と実用化の研究(ナノメーター物質の超精密物理化学・機械的制御をめざして) |
東京大学 |
助教授 |
黒田寛人 |
| 9 |
自動車用高強度アルミニウム合金板の成形限界の研究-実験とシミュレーション- |
東京農工大学 |
助教授 |
桑原利彦 |
| 10 |
セラミックスの破壊メカニズム解明と高信頼性セラミックス創製に関する研究 |
静岡大学 |
助教授 |
坂井田喜久 |
| 11 |
次世代型新粘性ダンパの開発 |
秋田県立大学 |
助教授 |
島田邦雄 |
| 12 |
新しい概念に基く有機・無機ハイブリッド低融点ガラスを用いた光機能性デバイスに関する研究 |
京都大学
化学研究所 |
助手 |
島田良子 |
| 13 |
自主的に組立が起こるナノマシン開発のための基礎研究 |
群馬大学 |
助教授 |
武田茂樹 |
| 14 |
新らしいクリープ理論の展開と合金設計手法の開発 |
防衛大学校 |
教授 |
田村学 |
| 15 |
強力サンドイッチ型超音波モータを用いたひざサポータの開発 |
東京農工大学 |
教授 |
遠山茂樹 |
| 16 |
Dual-Varifocal Lensシステムによる真実立体映像の実現 |
大分大学 |
助教授 |
中西義孝 |
| 17 |
スメクチック層回転を利用した光伝導膜を有する空間光変調素子の研究 |
静岡大学 |
助手 |
中山敬三 |
| 18 |
小型直接メタノール型燃料電池の開発とバイクへの応用 |
武蔵工業大学 |
教授 |
永井正幸 |
| 19 |
MRIにおける治療を支援するロボットの開発 |
秋田大学 |
助教授 |
長縄明大 |
| 20 |
スプリット噴射直噴ディーゼル噴霧の混合気特性とエンジン燃焼性能との関連解明 |
広島大学 |
助教授 |
西田恵哉 |
| 21 |
手首EMGに基づく次世代携帯端末用インタフェースの基礎研究 |
徳島大学 |
助教授 |
福見稔 |
| 22 |
顕微鏡観察を応用したパッシブ型大気粉塵サンプラーの開発 |
東京大学 |
助手 |
藤井実 |
| 23 |
衝突破壊試験で使用される力センサーの動的特性評価に関する研究 |
群馬大学 |
助教授 |
藤井雄作 |
| 24 |
衝撃的振動の影響を考慮した走行快適性予測モデルの開発 |
埼玉大学 |
助手 |
松本泰尚 |
| 25 |
高導電率プロトン伝導性酸化物薄膜の作製とその燃料電池電解質への応用 |
千葉工業大学 |
教授 |
山口貞衛 |
| 26 |
シャフトドライブCVT用変速機構の実現 |
東北大学 |
助教授 |
山中将 |
| 27 |
多孔質体のガス流動と反応の数値解析 |
豊橋技術科学大学 |
助手 |
山本和弘 |
| 28 |
階層構造を有する材料の変形特性のモデル化と加工解析手法の開発 |
名古屋大学 |
助教授 |
湯川伸樹 |
| 29 |
単結晶金属の極微細塑性加工による表面機能特性開発 |
東京工業大学 |
助教授 |
吉野雅彦 |