
- サステナビリティ
- スズキのサステナビリティ
-
基本的な考え方・推進体制
基本的な考え方・推進体制
サステナビリティに関する基本的な考え方
当社はこれまで、得意とするコンパクトな四輪車をはじめとするさまざまな製品の開発と普及を通じて、各国の社会的・経済的な発展に貢献してきました。
原点

1909年創業当時の鈴木式織機製作所
1908年、創業者である鈴木道雄が、“母を楽にしてあげたい”との想いから織機を手作りしたことが、鈴木式織機製作所の創業につながりました。この“お客様の課題を解決したい” という想いがスズキの原点です。織機事業から始まり、複数の事業を展開してきました。
モビリティ事業

パワーフリー号
1952年に発売した、自転車にエンジンを取り付けた「パワーフリー号」は、“楽に遠くまで走れる”とお客様に大変喜ばれ、当社の二輪の歴史がスタートしました。
その3年後には、日本初の量産軽自動車「スズライト」を発売し四輪事業に進出。その後、船外機、電動車いすの発売により現在の事業展開に至っています。
グローバル展開

マルチ・スズキ・インディア社でスズキ四輪車生産開始
長らく二輪車と四輪車の両方を扱ってきたという特長を持つ当社は、二輪車の持つ利便性や経済性を活かして、世界中でモータリゼーションの機会をいち早く捉えてきました。そうしてお客様との接点を増やしながら、その国や地域の経済成長とともに、二輪車から四輪車への普及と拡大の道を歩んできました。
グローバル展開における特に大きな転機は、1979年の「アルト」誕生です。常識を破る低価格で発売したアルトは大ヒットとなり、日本の軽自動車の市場を築くことができました。これが契機となり、ゼネラルモーターズとの業務提携の実現や、インド国民車構想のパートナーに選ばれ合弁会社を設立するなど、海外進出という大きな飛躍につながりました。さらに、インドでの評判がハンガリーに伝わり、欧州への工場進出を果たしました。
人々の豊かな暮らしのために

スズキ・モーター・グジャラート社
これまでも“進出国・地域とともに成長する”ため、海外での現地生産を進め、その地域のニーズに合った製品・サービスを提供することにより、市場を拡大し、経済発展に貢献してきました。
インドでは、1983年に現地で四輪生産工場の稼働を開始し、現在は年間235万台まで生産能力を拡大しています。また、工場進出の歴史は取引先の皆様との歴史でもあり、一緒に成長しながら歩みを進め、強固な調達網と9割を超える高い現地調達率を築き上げてきました。さらに、販売網・サービス網の拡大にも取り組み、地方の農村部まで広がったネットワークはスズキ最大の強みとなっています。近年では、現地での研究開発も加速させており、優秀な技術者の採用を積極的に進めています。このように、裾野が広い自動車産業において、生産、調達、販売、開発を通じて現地でたくさんの雇用を生み出しながら、インドの経済成長に貢献しています。2023年3月末にはインド国内累計販売3,000万台を達成しました。市場状況を見ながら適切なタイミングで生産能力を年間400万台まで引き上げる計画です。
人々の生活に寄り添って地域を支える

軽トラ市の様子(静岡県浜松市)
当社のものづくりの根幹である「小・少・軽・短・美」に基づいて生み出された製品は、コンパクトながら使い勝手が良く高性能で、お求めやすい価格を実現しています。多くの人々に移動の自由を提供することで、世界中で地域の生活を支えています。
日本では、特に公共交通機関が利用しにくい地方部において、使い勝手が良く経済性に優れた軽自動車が、生活の足としてなくてはならない存在となっています。さらに、軽トラックの荷台に食料品や地元の特産品、雑貨などの商品を陳列し、商店街に集まって販売する「軽トラ市」が全国の地方都市で毎年開催されています。少ないコストでたくさんのお客様を集めることができ、地方経済の活性化に貢献しています。
また、新興国では、当社が得意とするお求めやすく高性能なコンパクトカーが、初めて自動車を購入するお客様のニーズにマッチし、たくさんのお客様が自動車のある快適で豊かな暮らしを手に入れることができます。
スズキらしい解決策で
2022年7月に量産を開始した、世界初の船外機用マイクロプラスチック回収装置は、複雑で高価な装置ではなく、とてもシンプルな構造で部品代も抑えているという特長があります。水辺の清掃活動での雑談から始まった、誰でも思い付きそうで、誰もやらなかった装置のアイデアでしたが、「とにかくやってみよう」と積極的に挑戦し、試行錯誤を重ね、短期間で製品化に結び付けました。一人でも多くの人に使ってもらいたい、そのためには船外機の性能はそのままに、いかに簡単に、いかに安く作るか。「小・少・軽・短・美」に裏打ちされたスズキらしい創意工夫と想いを込めて作った製品を、楽しく使ってもらいながら、お客様と一緒に社会の課題を解決していきたいと考えています。
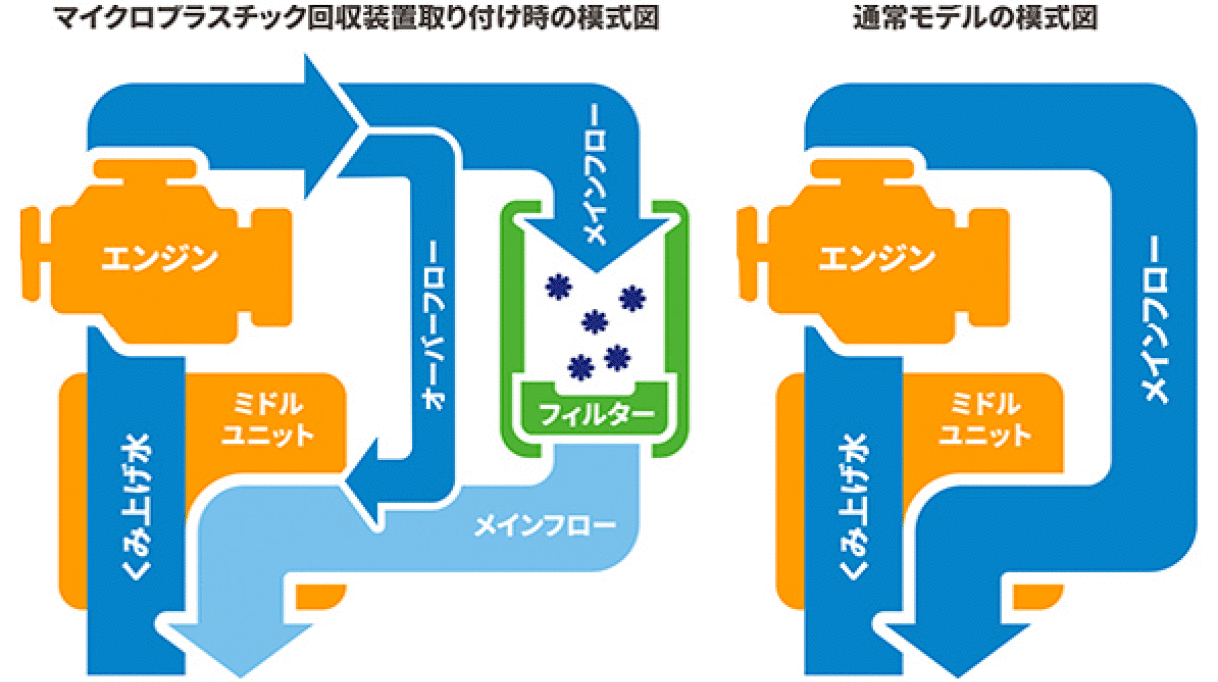
なくてはならない存在であり続ける
自動車産業が直面している諸課題の中でも、特に重視しているのがカーボンニュートラル達成に向けた電動化への取り組みです。カーボンニュートラルの達成には、走行時だけではない、総合的なCO2排出量の削減が求められており、車両の生産、電気などの燃料の精製の際に発生するCO2についても考える必要があります。
そうした考えのもと、当社はCO2の総合的な削減には、EVに加えて、ハイブリッド車、CNG車、バイオ燃料車、さらには水素を使ったモビリティを、それぞれの地域・市場に合わせ組み合わせながら進めること、「マルチパスウェイ」による進め方が重要と考えます。
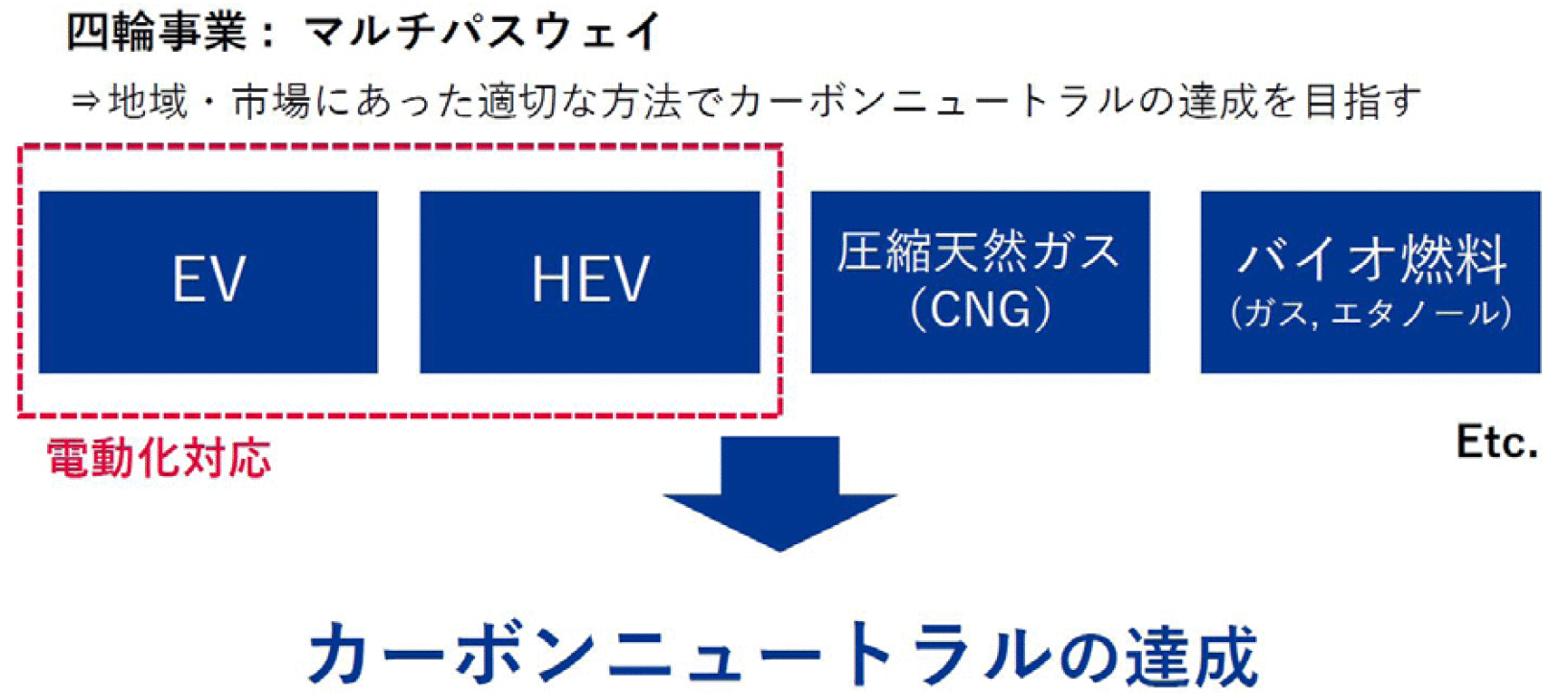
当社が得意とするコンパクトカーは、お求めやすさが支持されて多くの人々にご愛用いただいていますが、EV化による製品価格の上昇は、こうしたコンパクトカーのメリットを減らすことにつながりかねません。人々の生活になくてはならない存在であり続けるために、「小・少・軽・短・美」の思想を活かし、コストと航続距離や装備をバランスさせ、お客様のニーズと利用スタイルに対応した、いわば適所適材のEVを開発し市場に投入していく計画です。
また、当社独自の取り組みとして、インド農村部に多い酪農廃棄物である牛糞を原料とする、カーボンニュートラルなバイオガス燃料の製造・供給事業に挑戦しています。このバイオガス燃料は、インドCNG車市場シェアの約70%を占めるスズキのCNG車に使用することができ、実現すればお求めやすい価格で自動車の提供を続けることができます。インドのみならず、アフリカやASEANなどの新興国や、日本の酪農地域でも展開が可能な技術です。
これからも四輪車を中心に、二輪車、船外機、電動車いすなどのモビリティ事業を展開し、お客様の生活を支える製品・サービスを提供することで、社会課題の解決と企業の成長の両方を実現させ、人と社会に必要とされ続ける会社を目指します。

Banas Dairy社バイオガス精製プラント
(このプラントをもとにBanas Dairy社と当社が共同でプラントを建設中)
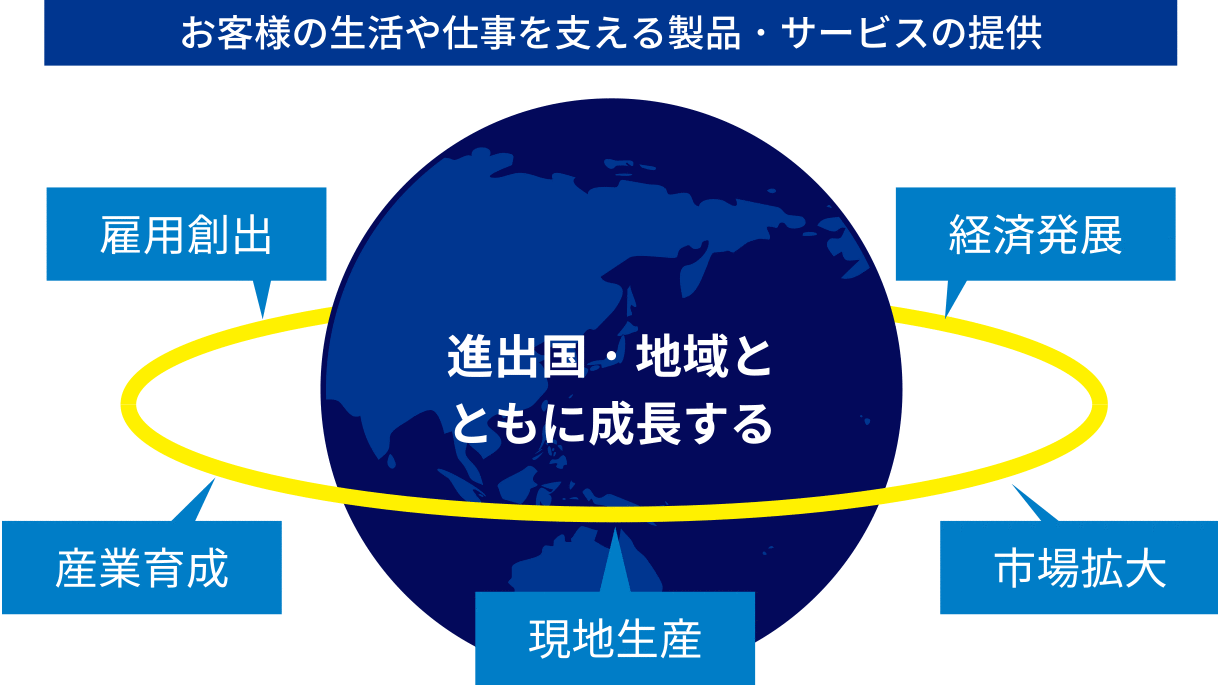
推進体制
サステナビリティ推進体制
(2025年6月現在)
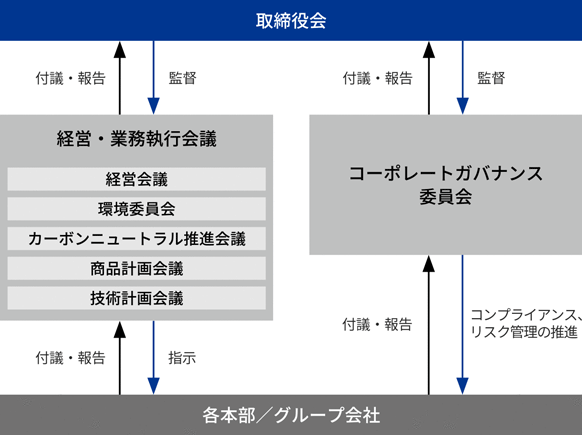
取締役会におけるサステナビリティ関連の主な議題(2024年度)
- カーボンニュートラル対応(EV・バイオガス関連)
- 人事戦略
- サプライチェーンの人権対応
- 知財ガバナンス 他
- 情報セキュリティ
- 社会課題解決の取り組み(NBV活動)他
代表取締役および関係役員が出席する「経営・業務執行会議」と「コーポレートガバナンス委員会」において、サステナビリティ(環境・社会・ガバナンス)に関する課題や方針、対策などについて議論しています。特に重要な議題については取締役会に上程・報告します。経営と一体となった、実効性のある活動の推進を目指しています。
具体的な施策については、経営企画本部に設置したサステナビリティ推進の専門部署を中心に、社内各本部/グループ会社と連携し、社会課題の解決に向けた取り組みを社内横断的に推進しています。
